活動報告:日本生徒指導学会 関西地区研究会 第18回大会
過去の活動報告はコチラ
テーマ:関西発!元気の出る生徒指導 ~発達支持的生徒指導の実現に向けて私たちができること~
日 時:令和7年8月3日(日)
場 所:和歌山大学(和歌山県和歌山市栄谷930)
1 はじめの挨拶
日本生徒指導学会副会長 関西地区研究会会長 新井 肇

本研究会は2008年、学校現場と大学等の研究機関の連携の重要性を掲げ、森田洋司先生のご尽力により発足し、理論と実践を繋ぐ場として継続している。今大会は240名が参加し、自由研究発表で10名の発表に加え、分科会も拡大することになった。不登校、いじめ、自殺、暴力行為等、学校が抱える危機的状況に向き合い、子供も教師も元気を取り戻す生徒指導の在り方を考える。テーマは「安全安心で魅力ある学校づくり」。参加者同士の学び合いを通じ、前向きな気持ちとなるきっかけとなることを願う。
2 開催地より挨拶
和歌山県教育庁学校教育局教育支援課長 窪田 光利

和歌山において本大会が盛大に開催されることを心よりお喜び申しあげる。急激な社会変化の中、生徒指導に真摯に取り組まれる本研究会の皆様の研鑽に深く敬意を表する。和歌山県教育庁としても、皆様の豊富な実践事例に学び、安全安心な魅力ある学校づくりを推進してまいる。また、高野山熊野古道等の聖地巡礼や温泉など、心身を癒す魅力にあふれる和歌山にもぜひお立ち寄りいただければ幸いである。本研究会の発展と、参加の皆様のご健勝とご活躍を祈念する。
和歌山大学大学院教育研究科教職開発専攻長 山田 真稔

関西地区で生徒指導に志を持つ皆様の大会が、本学教育学部で開催されることを嬉しく思う。社会の変化が著しい中において、生徒指導には多角的な最新アプローチが求められている。本日は講演や分科会、情報交換を通じて、互いに学び合い深め合える有意義な場となることを願っている。また、「元気の出る生徒指導」をこの和歌山から発信いただけることにも大いに期待している。
全体会「児童生徒理解に基づく安全・安心な魅力ある学校づくり」
千里金蘭大学 教授 阿形 恒秀
1.発表概要

児童生徒理解は、生徒指導の基礎として心理的・社会的な視点が求められる。教師は、児童生徒の心に寄り添う共感的な態度を持つことで信頼関係を築き、「心の居場所」を提供する役割を担う。安全安心な環境の実現とは、生徒が自己を認められる精神的な充実感を得る場の構築であり、監視に頼るのではなく、信頼と絆を育むことが教育の本質。教師同士の協働性も重要であり、互いを支え合うことで教育の質の向上、教師自身の安心感にも繋がる。生徒指導の転換期における「安全・安心で魅力ある学校づくり」とは何か。
2.発表要旨
教師の「児童生徒理解」は、生徒指導の基礎であり、心理面、学習面、社会面など多角的な視点から総合的に捉えるべきである。近年、学校において「心の問題はスクールカウンセラーに任せればいい」といった安易な判断がされる傾向を感じているが、それは教育者としての責任放棄に繋がる可能性がある。哲学者である鷲田清一氏も「カウンセラー任せでは教育者としての破産を自ら宣告しているようなものではないか」とされ、私自身も教師が主体的に児童生徒の心に寄り添う姿勢を求めている。臨床心理の専門家はあくまで「心理療法の専門家」であり、それを広義に「心の専門家」と表現するのは望ましくない。もちろん専門的治療が必要な場合は連携が不可欠だが、教師も「心の専門家」であるという意識が必要。
「心の構造」を理解することは、心理学や精神医学における大前提であり、特にフロイトによる「無意識」の発見は、現代でも臨床心理学の基本的な常識である。人間の心は、目に見える言葉や理屈だけでは語り尽くせない複雑な働きをしており、人が交わすコミュニケーションには、表面化しない感情や「無意識」の動きが常に存在している。とりわけ、教師が児童生徒と向き合う場面においては、この「心の構造」に対する深い理解が欠かせない。理屈のレベルで接するだけでは十分ではなく、臨床心理学の視点では、子どもと大人の間にある目に見えない心の動きや心理的ベクトルを汲み取ることが重要である。そうした理解がより深い信頼関係や効果的な支援につながると考えられる。
例えば、アメリカで社会問題となっていた「子どもの遺棄」をめぐるエピソードがある。ある男の子が、父に「去年、ニューヨークのハーレムでは何人の子どもが捨てられたの?」と尋ねる。父は驚きながらも調べて答えたが、翌日、「ニューヨーク全体では?」さらにその数日後には「アメリカ全体では?」と質問が続く。父は最後の問いの後、息子をハグし、「パパはお前を絶対捨てない」と言う。このやり取りは、一見すると論理的な会話ではないが、子どもの心の奥底にある「自分も捨てられるかもしれない」という無意識の不安に対す
る最適な答えである。子どもの問いの背後にある感情に気づき、寄り添った対応が信頼と安心を生む。
また、学校行事をめぐる生徒とのやりとりで、例えば「修学旅行は絶対行かなければいけないのですか?」という質問があった。表面的には、学校行事への反抗や面倒くさいという気持ちに見えるが、実際には「友人関係で悩んでおり、宿泊先で同じ部屋になるのが苦痛である」など、複雑な事情があるかもしれない。このような時、教師が「行かないといけない」と正論で応じてしまうと、生徒は「相談しても受け止めてもらえない」と感じるだけである。「どうして行きたくないの?」と問い返し、対話を始めることで、真の支援が生まれる。大切なのは、「知的理解」にとどまらず、「感情移入的理解」をもって生徒を受け止めることである。共感的に理解されることで、子どもたちは安心し、自分の悩みを打ち明けられるようになる。なお、問題が深刻である場合には、スクールカウンセラーなどとの連携を通じて、専門的な支援につなげることも必要である。
学校における「安全安心」いう言葉は、生活安全、交通安全、災害安全、防災教育などが含まれる。しかし生徒指導の観点からの「安全安心」は、より深く意味を捉え、「安全安心な風土の醸成」が重要な視点となる。これは国立教育政策研究所の資料にも定義されているが、いじめ、暴力等の問題が起こらないだけでなく、生徒が精神的に安定し、自己の存在感を実感できたり、充実感を得られたりする「【心の居場所】を持てる環境づくり」が必要だということである。
生徒指導上の諸課題に対し、単に「問題発生を抑え込めばいい」という発想では不十分であると考える。核抑止の話に例えると、広島平和記念式典での知事の発言を例に、【お互いに核兵器を持ってけん制し合う】といった抑止力による安心は本質的ではなく、「どうすれば隣人と仲良くできるか」という視点が大切だと語られた。これは教育におけるいじめ対策にも通じ、抑止的な手段より、関係性や風土づくりが重要であると考える。
イギリスの学校ではいじめ対策としての抑止の一環として教室に監視カメラが設置されている。日本でも自治体によって教室への監視カメラ設置が進められており、監視によって証拠を残すという利点もあるものの、生徒の伸びやかさが失われる可能性もある。【教育の本質は、人間の眼差しによる関わり】という観点を持つ必要がある中、どう向き合うか問われている。
結局のところ、「安全安心」とは、問題を未然に防ぐだけでなく、生徒が心から安心できる居場所をどう作るかという視点に立つべきであり、今日の自由研究や分科会のテーマもこの考えに深く関わっている。教育の目的は、抑止ではなく信頼と絆を育むことである。今大会に向けて、本研究会では多くの議論を重ねてきた。特に「安全・安心」というテーマの主語が誰なのかという問いから始まり、児童生徒だけでなく、「教師自身の安全安心も重要である」という認識が深まった。教師が元気であることが教育の質に直結するという視点は、森田洋司先生の「教師が主語」という言葉にも表れている。
教職のやりがいについても多くの示唆があった。子どもの笑顔や成長が最大の報酬であり、同僚との共同性も大きな支えとなる。かつて勤めた学校では、コーヒーメイトのような小さな習慣が共同性を象徴していた。組織が機能するとは、指先の痛みを体全体で感じるような、互いの気づきと支え合いがあることだと実感している。
また、「させる生徒指導から支える生徒指導へ」という転換も重要なテーマである。単なる課題対応ではなく、自己指導能力の育成をめざす支援が求められており、表面的な指導ではなく、内面からの変容を促すことが本質であり、教育の深さを問うものと考える。
最後に、本研究会の強みは、多様な立場の人々が集い、知恵を出し合えることにある。専門性の細分化ではなく、全体性を重視し、魂に触れるような教育の在り方を模索する場で あることを改めて感じた。本大会が、教師のやりがいや、教育の本質を深める契機となることを心から願っている。
シンポジウム
ファシリテーター: 日本生徒指導学会副会長 日本生徒指導学会関西地区研究会会長 新井 肇
シンポジウムの概要



立場の異なる4名のシンポジストが、「児童生徒理解に基づく安全・安心な魅力ある学校づくり」に関する各項目について、市町村教育委員会の取組、学校の取組による話題提供を行う。
- 「安全安心な魅力ある学級作りの研究事業について」
和歌山県教育庁教育局教育支援課 専門員 馬場 敦義
同 指導主事 松本 穣 - 「安全安心な魅力ある学級作りの実践について」
海南市立大東小学校 教諭 小田川 知晶 - 「安全安心な魅力ある学級作りの研究事業について」
京都市立洛風中学校 校長 芦田 美香
自由発表
第1会場: 「1人1台端末を活用した心の健康観察~全ての児童生徒を対象にしたプロアクティブな生徒指導~」
京都府教育庁指導部学校教育課 指導主事 山下 英孝
発表概要
都道府県教育委員会が作成した心の健康観察ツールの活用を軸にした「1人1台端末を活用した心の健康観察とプロアクティブな生徒指導」についての発表であった。児童生徒が日々の心身の状態を端末で記録することで、教員が早期にリスクを把握し、迅速な支援につなげる仕組みを紹介。使用する学習eポータルの「毎日の記録」機能を活用し、心身の状態、安全安心な風土、育みたい力の3つの観点から児童の状況を把握する。従来の「深刻化を防ぐ」指導から一歩進め、子どもたちの成長を促す「プロアクティブな生徒指導」を目指す姿勢が示された。導入により、児童の自己表現力や教員の対応力が向上し、不登校やいじめの予防にも効果が見られた。
第1会場: 「1人1台端末を活用した心の健康観察とチーム学校の形成」
滋賀県栗東市立栗東中学校 校長 住吉 由加
発表概要
「1人1台端末を活用した心の健康観察とチーム学校の形成」についての発表であった。外部支援や専用アプリは用いず、学校でGoogleフォームを独自にカスタマイズして運用。生徒の気分、睡眠、朝食状況などを簡易的に記録し、支援チームが週1回分析を行うことで、教員の負担を軽減しつつ早期支援につなげている。入力データからは、支援が必要な生徒の傾向や生活習慣との関連が明らかになり、養護教諭やSSWなど多職種が連携して対応。結果として教員間の会話が増え、学校全体で生徒を支える「チーム学校」の実現につながった。発表では実践の工夫と課題、今後の展望についても具体的に語られた。
第2会場: 「今年度開校した学びの多様化学校の現状」
神戸市教育委員会事務局児童生徒課 指導主事 河野 悟
発表概要
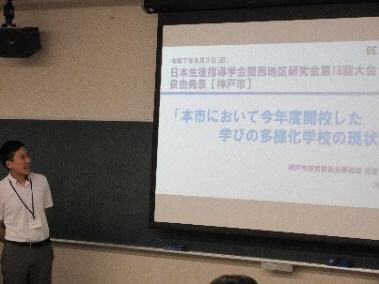
神戸市では令和5年度の小中高における不登校児童生徒数が4,500名を超え、その支援については重要な課題であると認識している。令和5年7月に「不登校支援の充実に向けた基本方針」を策定し、不登校支援相談センターの設立、オンラインによる相談場所の整備、メタバースを活用した居場所づくり、全小中学校での校内サポートルームの設置、市内の教育支援センターを8か所から9か所に増設するなど、様々な不登校支援策を展開してきた。加えて、新たに今年度「学びの多様化学校」を神戸市立湊翔楠中学校分校として開校した。現在は1年21名、2年9名、3年11名の計41名が在籍している。開校から1学期間の「生徒の様子、家庭との連携、並行して行われる次年度の生徒募集、体験学習、学習環境について」等の現状や結果についての実践報告とする。
第2会場: 「登校を目的化しない時代に、学校は不登校の子どもに何ができるのか」
~ASEBAによるアセスメントに基づく不登校・不適応の子どもへの対応~
泉佐野市立新池中学校 教諭 宮内 裕史
発表概要

〇不登校児童生徒数が過去最多を更新し続けており、「登校のみを目的としない」支援が求められている中、ASEBA(Achenbach System of Empirically Based Assessment:心理社会的な適応・不適応状態を包括的に評価するシステム)を活用したアセスメントに基づく支援の実践報告。
〇従来の「子どもの失敗を待つ支援モデル(discrepancy(相違)モデル)」から脱却し、RTI(Response to Intervention)モデルに基づく3層構造の支援体制を導入し、子どもの心理社会的適応・不適応を可視化することにより、支援方針を立てて対応していくことを提案。
第3会場: 「課題予防的生徒指導の充実を目指した研究」
~日常的な心の可視化から非認知能力育成へのつながりを意識して~
岩出市立根来小学校 教諭 森脇 拓也
発表概要

「子どもたちの発信する問題行動やSOSは、非認知能力の育成により、自ら乗り越えていけるようになるのではないか。」という仮説のもと、「課題予防的生徒指導」の充実を図ることを通して、児童の非認知能力の育成を目指した。
手立てとしては、(1)子どもの「心の状態を日常的に可視化」、(2)「児童の非認知能力の把握・育成」、(3)生徒指導部会の役割の再整理を行った。結果、悩みを抱える児童の早期発見・対応を進めることができた。また、非認知能力の指標を設けたことで、評価基準が明確になり、教員が多角的な視点で児童を見つめ直すきっかけになった。生徒指導部会が、教員間の情報共有を促進し、学年間の指導のずれを調整する機能を果たすことができるようになった。
第3会場: 「発達支持的生徒指導の実現に向けた特別活動の可能性に関する研究構想について」
芦屋市教育委員会学校支援課 主査 池原 征紀
芦屋市立潮見中学校 教諭 小林 則好
発表概要

本市の中学生は、全国学力・学習状況調査において学力面では良好な結果を示しているが、主体的に問いを立て、深い学びにつなげるような教育的営みに課題がある事が示唆される。生徒が話し合いを通じて、意思決定を行う機会を設け、段階的に活動の主導権を委ね、自分たちが学校という社会の作り手であるという意識を持つことを目指したり、各学年の生徒指導担当が職員室内において意図的に職員間の対話を促す働きかけを行うことで、実践と省察が連動する体制づくりを進めることで、教員間での生徒指導観の共有と対話を促進し、職員室における心理的安全性と同僚性の醸成をめざしたりする。こうした取組を通して、特別活動が発達支持的生徒指導の実践の場となりうる可能性を明らかにしたい。
第4会場: 「複合的な困難を抱える子を支える『チーム学校』」
~支援を要する子をつなぐ教育と福祉の新たな協働の再考~
大阪大学大学院 人間科学研究科 教育環境講座 教育文化学研究生
滋賀県教育委員会 SSW SV 社会福祉士 上村 文子
発表概要
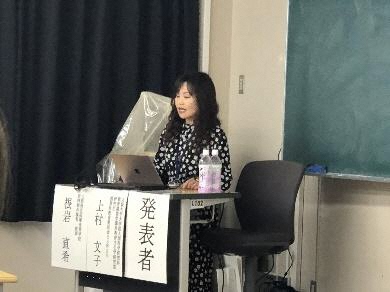
1 はじめに
2 先行研究の検討
3 インタビュー調査の概要
4 主な知見 (1) (2)
5 おわりに
第4会場: 夜間定時制高校における生活指導の課題と実践
~外国ルーツの生徒への支援の取組~
大阪府立桜塚高等学校 定時制の課程教頭 根岩 直希
発表概要

1 定時制に通う生徒たちの変化について
・大阪府高等学校定時制通信制教育研究会生活指導研究会の活動記録の分析を通して
2 外国にルーツを持つ生徒たちへの支援について
第5会場: 「課題予防的生徒指導(課題早期発対応)を目指した取組」
~子どもたちの日々の心情の可視化~
和歌山県九度山町立河根小中学校 教諭 植木 雅明
発表概要

和歌山県九度山町立河根小中学校で令和6年度から児童生徒の心情の可視化を実践した。児童生徒は朝、登校後に一人一台端末でその日の心情や体調を入力することにより、教員は児童の様子を客観的に把握することができた。また必要に応じて児童生徒は教員等に相談希望を入力することができ、SOSを出す一助となった。
第5会場: 「出会いが人を変える」
熊取町立熊取北中学校 校長 齊藤 貴英
発表概要

自身の少年時代や教員生活において「教員と生徒が信頼関係を築くことが教育の基盤である。」と強く感じた。デジタル化が進む中、体験活動などのアナログな関わりが効果を発揮すると考えており、教員が本気で生徒に関わることで、生徒もその思いに応えると考えている。参加者にもそのような思いをもった教員になってほしいと感じている。
分科会
第1分科会: 兵庫版「自殺予防教育プログラム」の作成
~より実効性が高く活用しやすいプログラムをめざして~
| 講演・発表者 | 兵庫県立総合教育センター心の教育推進課 課 長 横山 恵子 同 指導主事 福田 裕子 |
|---|---|
| 座長・司会 | 井上 浩史(関西地区研究会常任幹事) |
発表概要
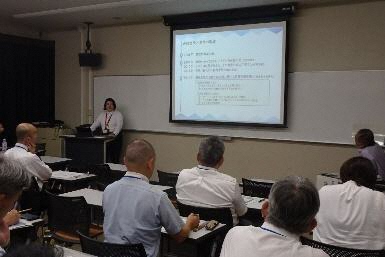
1 自殺対策と本県の取組
2 「自殺予防に生かせる教育プログラム」の概要
(1) 作成当時(2017年)のねらい
(2) プログラムの構成
(3) 「こころの健康に関するアンケート」を活用した効果測定
3 自殺予防教育について
(1) 子どもの自殺の現状、推移
(2) 自殺予防教育の構造(核となる授業、下地づくりの授業、安全・安心な学校環境)
4 兵庫版「自殺予防教育プログラム」について
(1) 自殺予防教育プログラム実践校等の調査研究
(2) 兵庫版「自殺予防教育プログラム」の概要
5 自殺予防教育担当者を対象とした研修会の開催
第2分科会: 「児童が安心して成長できるSSRのあり方」
~「人とのつながり」「安心できる環境づくり」「周囲の理解」を軸にしたSSRの充実に向けた取組を通して~
| 講演・発表者 | 滋賀県総合教育センター 研修指導主事 唐﨑 展之 同 研究員 田中 彰 滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課児童生徒室 主 査 藤本 友紀 同 指導主事 有馬 純一郎 |
|---|---|
| 座長・司会 | 阿形 恒秀(関西地区研究会副会長) |
発表概要

児童が安心して成長できるSSRのあり方について、「人とのつながり」「安心できる環境づくり」「周囲の理解」の三つの要素を軸に支援を充実させることで、子どもの社会的自立に向け、SSRが児童にとって安心して成長できる場となることを目指した。今回は、滋賀県のSSRについて以下のように発表した。
1 滋賀県のSSRについて
(1) SSRの設置率と課題について
(2) SSRの効果について
2 滋賀県総合教育センターのSSR研究について
(1) 研究の内容
(2) 成果と課題
第3分科会: 「京都市の不登校児童生徒支援の取組」
~教育メタバースを活用した居場所と校内サポートルームの進捗~
| 講演・発表者 | 京都市教育委員会指導部 生徒指導課 首席指導主事 水野 博之 同 副主任指導主事 赤井 範子 同 担当係長 藤元 剛史 |
|---|---|
| 座長・司会 | 片山 紀子(関西地区研究会副会長) |
発表概要

1 京都市の不登校児童生徒支援への支援施策
・不登校児童生徒の増加
・不登校児童生徒への支援施策
〇学校における取組
校内委員会「登校支援委員会」(生徒指導委員会)常設、アセスメントシートの活用、クラスマネージメントシート、校内サポートルームの整備
〇相談窓口 京都市教育相談総合センター(パトナ)
〇多様な学びの機会確保
ふれあいの杜、学びの多様化学校(洛風中学校・洛友中学校)、メタバースを活用 した支援、フリースクール連携事業・情報提供、京都奏和高校
2 教育メタバースを活用した「オンラインの居場所」
3 京都市の校内サポートルームについて~中学校を中心に~
第4分科会: チーム三重でいじめ問題から子どもを守る!
~いじめ対応情報管理システムを活用した迅速かつ適切な対応~
| 講演・発表者 | 三重県教育委員会事務局 生徒指導課 生徒指導班 |
|---|---|
| 座長・司会 | 池田 忠(関西地区研究会副会長) |
発表概要

本分科会では、いじめ問題に係る三重県の現状と未然防止の取組、学校と市町教育委員会、県教育委員会が連携した対応について発表した。
特に、昨年度から運用を開始している、学校と市町教育委員会、県教育委員会がいじめの対応情報を遅滞なく共有する「いじめ対応情報管理システム」について、システムの概要や運用初年度の成果と課題、今後の対応方針等について紹介した。
第5分科会: 「大阪府発! 教職員の同僚性・協働性の備わった学校づくりにむけて」
| 講演・発表者 | 大阪府教育庁市町村教育室小中学校課 参事 中野 悟志 同 生徒指導グループ 主任指導主事 家村 憲治 |
|---|---|
| 座長・司会 | 新井 肇(関西地区研究会会長) |
発表概要

いじめや不登校等の生徒指導上の諸課題への対応や、「発達支持的生徒指導」の取組に進捗が見られる学校では、校内の教職員間で目的等を共通理解し、「チーム学校」として取り組めるよう働きかけることをポイントとしている。本分科会ではそうした教職員の同僚性・協働性を備えるための参考となる具体的な実践や工夫についてお伝えする。
 [PDF版]全ページダウンロード
[PDF版]全ページダウンロード